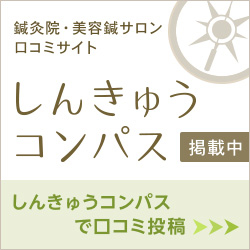同心整骨院コラム
2024年12月 9日 月曜日
こむら返り♪
夜寝ていると足が引きつって痛い!といった経験はありませんか?
その足の引きつりは「こむら返り」ともいい、寝てるとき以外にも運動している時などにも起こり
いったん引きつると収まるまで待っておくしかないといった辛さもあります。
この足の引きつりの原因は、一般的には栄養不足や水分不足、冷え、熱中症、急激な寒暖差が原因で起こることがあります。
特に、寝ている時は汗をよくかいていることが多く脱水傾向になりやすいせいで足の引きつりを起こしやすいです。
ミネラルバランスの乱れ、血行不良、筋力低下、体温低下などがあり、重い布団をかけて寝ることも足の引きつりの原因になったりもします。
特に、先程も言ったように寝ている時はコップ一杯分ほどの汗をかくと言われているので、水分不足が原因のことが多くあります。
足が引きつった時の対処法は一般的にはビタミンEを取ってあげるといいと言われています。
あとはミネラル、水分をしっかり取ってあげると症状の改善ができますので是非しっかりと取ってあげてください!
おススメの食材は大豆や、ナッツ類、バナナやトマト、みかんなどがおススメです★

その足の引きつりは「こむら返り」ともいい、寝てるとき以外にも運動している時などにも起こり
いったん引きつると収まるまで待っておくしかないといった辛さもあります。
この足の引きつりの原因は、一般的には栄養不足や水分不足、冷え、熱中症、急激な寒暖差が原因で起こることがあります。
特に、寝ている時は汗をよくかいていることが多く脱水傾向になりやすいせいで足の引きつりを起こしやすいです。
ミネラルバランスの乱れ、血行不良、筋力低下、体温低下などがあり、重い布団をかけて寝ることも足の引きつりの原因になったりもします。
特に、先程も言ったように寝ている時はコップ一杯分ほどの汗をかくと言われているので、水分不足が原因のことが多くあります。
足が引きつった時の対処法は一般的にはビタミンEを取ってあげるといいと言われています。
あとはミネラル、水分をしっかり取ってあげると症状の改善ができますので是非しっかりと取ってあげてください!
おススメの食材は大豆や、ナッツ類、バナナやトマト、みかんなどがおススメです★

投稿者 同心整骨院 | 記事URL
2024年12月 6日 金曜日
寝違えとは?
こんにちは!
朝起きると、首の後ろから肩にかけて急に痛みが出ていることがありませんか?
これが「寝違え」と呼ばれるもので、ケガではなく、首の周囲の筋・腱・筋膜などの急性炎症です。
この症状は首が痛んで一定の方向にしか動かせないこともあり、仕事や家事などの活動にも影響がでます。
強い痛みで寝不足になったり、頭痛や背中の痛みにまで及ぶことも少なくありません。
症状が悪化すると首を支える筋肉が硬くなり、
痛みだけでなく違和感が慢性化したり、頭痛、めまい、しびれなど病気に繋がる原因になります。
寝違えの主な原因は、睡眠時の姿勢です。
不自然な姿勢で眠り続けると一部の筋肉が阻血という血液の供給が不足の状態に陥り、部分的にしこりになります。
通常は無意識に寝返りをうって、首に負担がかからない体勢に戻りますが、
寝ている場所が狭くなったり、枕があわないと不自然な体勢のまま眠り続けてしまう事があるのです。
もし、過労や泥酔状態で寝返りが打てないと、長時間にわたって首回りの筋肉に負担をかけて寝違いを起こすこともあります。
また、内臓の疲れや痛みが原因となって、睡眠中の姿勢が偏ったり、寝返りが少なくなり寝違えることもあります。
本日はここまでとなります。

朝起きると、首の後ろから肩にかけて急に痛みが出ていることがありませんか?
これが「寝違え」と呼ばれるもので、ケガではなく、首の周囲の筋・腱・筋膜などの急性炎症です。
この症状は首が痛んで一定の方向にしか動かせないこともあり、仕事や家事などの活動にも影響がでます。
強い痛みで寝不足になったり、頭痛や背中の痛みにまで及ぶことも少なくありません。
症状が悪化すると首を支える筋肉が硬くなり、
痛みだけでなく違和感が慢性化したり、頭痛、めまい、しびれなど病気に繋がる原因になります。
寝違えの主な原因は、睡眠時の姿勢です。
不自然な姿勢で眠り続けると一部の筋肉が阻血という血液の供給が不足の状態に陥り、部分的にしこりになります。
通常は無意識に寝返りをうって、首に負担がかからない体勢に戻りますが、
寝ている場所が狭くなったり、枕があわないと不自然な体勢のまま眠り続けてしまう事があるのです。
もし、過労や泥酔状態で寝返りが打てないと、長時間にわたって首回りの筋肉に負担をかけて寝違いを起こすこともあります。
また、内臓の疲れや痛みが原因となって、睡眠中の姿勢が偏ったり、寝返りが少なくなり寝違えることもあります。
本日はここまでとなります。

投稿者 同心整骨院 | 記事URL
2024年12月 3日 火曜日
側弯症ってなぁに?
こんにちは!!
本日は側弯症です。
側弯症は脊柱を後ろから見た際に左右に湾曲している状態のことを言います。
側弯症には一時的に側弯する機能性側弯と背骨のねじれを伴う構造的側弯に大きく分けられます。
構造的側弯のほとんどは特発性、つまり原因がわからないまま進行し、思春期の女子に多く起こります。
程度にもよりますが起こりうる症状として身体の痛みが上げられます。
脊柱が左右に湾曲すると片側の筋肉に負担がかかり、筋肉の凝りなどに繋がります。
これらがひどくなってくると神経症状が出る場合もあるので注意が必要です。
また女性の方が悩まれることが多いのは外見上の異常です。
ウエストライン、肩の高さが違うなど見た目の問題も発生していきます。
変形がひどくなれば手術での治療となりますが軽症なら装具で様子を見る場合が多く見られます。

本日は側弯症です。
側弯症は脊柱を後ろから見た際に左右に湾曲している状態のことを言います。
側弯症には一時的に側弯する機能性側弯と背骨のねじれを伴う構造的側弯に大きく分けられます。
構造的側弯のほとんどは特発性、つまり原因がわからないまま進行し、思春期の女子に多く起こります。
程度にもよりますが起こりうる症状として身体の痛みが上げられます。
脊柱が左右に湾曲すると片側の筋肉に負担がかかり、筋肉の凝りなどに繋がります。
これらがひどくなってくると神経症状が出る場合もあるので注意が必要です。
また女性の方が悩まれることが多いのは外見上の異常です。
ウエストライン、肩の高さが違うなど見た目の問題も発生していきます。
変形がひどくなれば手術での治療となりますが軽症なら装具で様子を見る場合が多く見られます。

投稿者 同心整骨院 | 記事URL
2024年11月27日 水曜日
膝の内側が痛くなる鵞足炎とは?
こんにちは!
今回は割とよく聞く膝の痛み、特に内側の痛みについての一例をお話しようと思います!
鵞足炎とは、膝の内側に付着する筋肉の滑液包という部分が炎症を起こしてしまう疾患です。
鵞足(がそく)とは、縫工筋、半腱様筋、薄筋と呼ばれる筋肉の腱が骨にくっつく部位です。
この部位にある滑液包という関節に存在するゼリー状の袋が炎症を起こしてしまいます。
炎症を起こしてしまう原因として、膝の屈曲や股関節の内転動作によって負担が繰り返しかかり慢性的な痛みを生じてしまいます。
アスリートなどに多いです。
アスリートだけでなく、膝の変形が見られる人にも多く発症します。
痛みの特徴は、膝の内側の少し下あたりが痛む事と、腫れや押すと痛い、熱感などが生じます。
セルフケアとして、太ももの裏側や太ももの内側のストレッチをしてあげると痛みが少しマシになったりもしますので、ぜひ行ってみて下さい。
本日はここまでとなります!

今回は割とよく聞く膝の痛み、特に内側の痛みについての一例をお話しようと思います!
鵞足炎とは、膝の内側に付着する筋肉の滑液包という部分が炎症を起こしてしまう疾患です。
鵞足(がそく)とは、縫工筋、半腱様筋、薄筋と呼ばれる筋肉の腱が骨にくっつく部位です。
この部位にある滑液包という関節に存在するゼリー状の袋が炎症を起こしてしまいます。
炎症を起こしてしまう原因として、膝の屈曲や股関節の内転動作によって負担が繰り返しかかり慢性的な痛みを生じてしまいます。
アスリートなどに多いです。
アスリートだけでなく、膝の変形が見られる人にも多く発症します。
痛みの特徴は、膝の内側の少し下あたりが痛む事と、腫れや押すと痛い、熱感などが生じます。
セルフケアとして、太ももの裏側や太ももの内側のストレッチをしてあげると痛みが少しマシになったりもしますので、ぜひ行ってみて下さい。
本日はここまでとなります!

投稿者 同心整骨院 | 記事URL
2024年11月25日 月曜日
足の裏が痛くなる足底筋膜炎とは?
足底筋膜炎とは、足のアーチ構造を支える足底腱膜といって、かかとの骨から足の付け根にかけて
繊維状の腱が膜のように広がっています。それが足底腱膜です。
足底腱膜は足底の土踏まずを保持して、歩行やランニングによる衝撃を吸収する役割があります。
足底筋膜炎の原因はランニングやジャンプをする動作などで足を着地させた時の力と、
足を蹴り出す時の力を繰り返されることで足底筋膜にかかる負担が大きくなり炎症や細かい断裂が引き起こされ、かかとや足の裏に痛みが生じます。
炎症が起こると動き出すと痛みが出るようになり、慢性化するとかかとの骨に骨棘と呼ばれるトゲの様な突起が出来て、さらに痛みが増すことがあります。
症状の強さによってはストレッチなどで柔軟性を上げることで痛みを抑えることも可能です!
アキレス腱やふくらはぎ、足の裏を伸ばすようなストレッチを行うと足底にかかる負担を軽減できます。
足の裏のストレッチは、足底が伸びるのを意識しながら足のかかとから足首にかけてゆっくり反らします。
10回1セットとして、1日3セット以上を目標にするといいです!

ふくらはぎやアキレス腱のストレッチは、右足を前にして前後に足を開きます。
両足ともかかとは床につけるのがポイントです。
右ひざをゆっくりと曲げて、左足のふくらはぎを伸ばします。
壁を押しながらすると体重が後ろの足にかかりやすくなって効果的です。

繊維状の腱が膜のように広がっています。それが足底腱膜です。
足底腱膜は足底の土踏まずを保持して、歩行やランニングによる衝撃を吸収する役割があります。
足底筋膜炎の原因はランニングやジャンプをする動作などで足を着地させた時の力と、
足を蹴り出す時の力を繰り返されることで足底筋膜にかかる負担が大きくなり炎症や細かい断裂が引き起こされ、かかとや足の裏に痛みが生じます。
炎症が起こると動き出すと痛みが出るようになり、慢性化するとかかとの骨に骨棘と呼ばれるトゲの様な突起が出来て、さらに痛みが増すことがあります。
症状の強さによってはストレッチなどで柔軟性を上げることで痛みを抑えることも可能です!
アキレス腱やふくらはぎ、足の裏を伸ばすようなストレッチを行うと足底にかかる負担を軽減できます。
足の裏のストレッチは、足底が伸びるのを意識しながら足のかかとから足首にかけてゆっくり反らします。
10回1セットとして、1日3セット以上を目標にするといいです!

ふくらはぎやアキレス腱のストレッチは、右足を前にして前後に足を開きます。
両足ともかかとは床につけるのがポイントです。
右ひざをゆっくりと曲げて、左足のふくらはぎを伸ばします。
壁を押しながらすると体重が後ろの足にかかりやすくなって効果的です。

投稿者 同心整骨院 | 記事URL